“見えない遺品”が増えている時代

現代では、スマートフォンやパソコンの中に大切な情報や資産が保存されていることが当たり前になっています。
しかし、本人が亡くなった後、これらの情報に家族がアクセスできず、困ってしまうケースが増えています。
こうした「見えない遺品」のことをデジタル遺品と呼びます。
メール、SNS、クラウド、ネット銀行、仮想通貨まで、扱いを誤ると大きなトラブルに発展する可能性もあります。
デジタル遺品に該当するもの一覧

デジタル遺品に該当する代表的なものには、以下のようなものがあります。
- スマートフォン本体(写真・メモ・アプリ)
- SNSアカウント(LINE、Instagram、Facebookなど)
- メールアドレス・クラウドサービス(Gmail、iCloud、Google Drive)
- ネットバンキング、証券口座、仮想通貨ウォレット
- オンラインストレージに保管された個人データ
- 定額サブスクリプション契約(Netflix、Amazonプライムなど)
「資産」として価値があるものに加え、個人情報が外部に流出するリスクもあるため注意が必要です。
遺族が直面する3つのトラブルとは
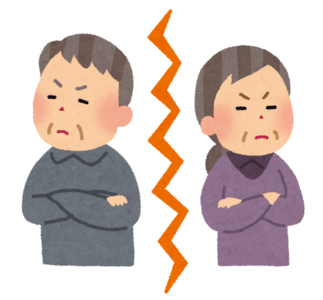
デジタル遺品を巡って、遺族が抱える代表的なトラブルには次のようなものがあります。
● ロック解除ができない
スマホやパソコンにパスワードがかかっており、そもそも中身を確認できない。
解除には本人の指紋やFace IDが必要なケースも。
● 解約・削除ができない
故人のSNSや契約中のサービスにログインできず、解約手続きが進まない。
中には費用が毎月発生し続けるサービスも。
● 資産の存在がわからない
ネット銀行や仮想通貨口座があること自体に気づかず、相続漏れが発生するケース。
今からできるデジタル遺品対策

こうしたトラブルを避けるために、元気なうちからできる備えがいくつかあります。
● パスワード・ID管理ノートを作る
信頼できる家族や専門家に引き継げるよう、パスワードを一覧化する。
紙でもクラウドでもOKですが、定期的な更新が大事です。
● アカウント整理・不要サービスの解約
使っていないサブスクや放置アカウントをこの機会に整理しておく。
● デジタル終活サービスの活用
「エンディングノートアプリ」「デジタル遺品引き継ぎサービス」などを活用する方法もあります。
家族と共有しておきたい“見えない遺品リスト”

家族がスムーズに整理できるよう、最低限以下の項目は共有しておくのが理想です。
- 使用しているスマホやPCの種類とロック解除方法
- よく使うメールアドレス、SNSアカウント
- ネット銀行・証券口座の存在有無
- 利用中の定額サービス(有料・無料問わず)
「書いておくほどでもないかな」と思うことが、死後には重要な情報になることがあります。
まとめ:デジタル遺品も“生前の備え”が大切

デジタル遺品は、形がないからこそ「遺された人」が困るものです。
逆に言えば、ほんの少しの備えで大きな負担を軽減できるとも言えます。
終活というと財産や保険が中心になりがちですが、
この“見えない資産”への備えこそ、これからの時代に欠かせないものになるでしょう。


