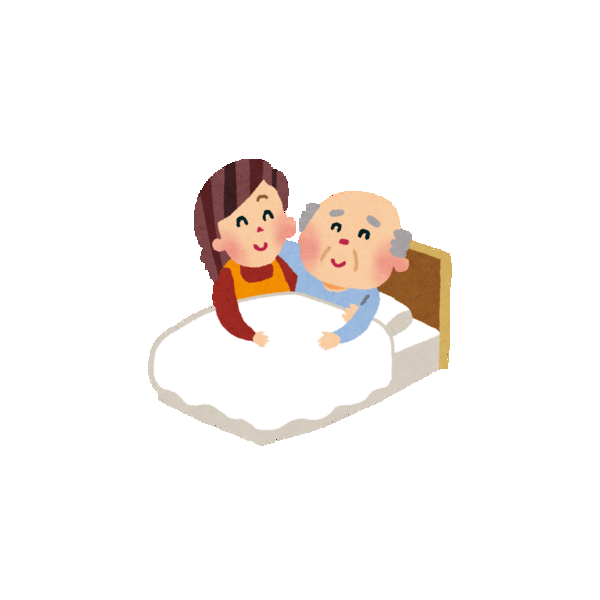突然始まった「終わりの準備」

「身近な人の最期にどう向き合えばいいのか―」
これは誰にとっても避けられないテーマですが、実体験に触れる機会は意外と少ないものです。
私の友人が体験した“お父様を看取るまでの道のり”は、その現実を教えてくれる貴重な経験でした。
連絡が来たのは春先で、すでにお父様の病状は進行しており、「数ヶ月以内」と医師から告げられていたそうです。
最初は「延命治療を続けるかどうか」など、判断を迫られる場面が何度もあったといいます。
感情が追いつかないまま、手続きや生活の準備を進める日々。
「時間が限られている」とわかっていても、現実には戸惑いや不安の連続だったそうです。
「やっておいてよかったこと」と「後悔していること」

友人が「やっておいて本当によかった」と語るのは、次の3つです:
- エンディングノートを一緒に書いた
- 最期を迎える場所を事前に選んだ(自宅 or ホスピス)
- 家族・親族との役割を共有した
一方で、「もっとやっておけばよかった」と感じたこともあったそうです:
- 思い出話をゆっくり聞く時間を持つべきだった
- 一緒にたくさん写真を撮っておけばよかった
- 死後の手続きの流れを早めに調べておくべきだった
どれも“その時”が来て初めて実感したことばかりだと話してくれました。
看取りは「一人で抱え込まない」ことが大切

看取りの現場では、感情・手続き・費用・人間関係など、多くの負担がのしかかります。
友人は、「最初はすべて自分で頑張ろうとしていたけれど、途中で限界が来た」と話してくれました。
地域包括支援センター、在宅医療の看護師、葬儀社の相談窓口など、頼れる存在は意外とたくさんあります。
「看取りは、家族だけの問題ではなく、地域や専門職の支えが大きな力になる」――
このことをもっと早く知っていれば、もっと穏やかに過ごせたかもしれないとも感じたそうです。
まとめ

今回の体験談を通して強く感じたのは、「看取りは“準備”と“共有”が鍵になる」ということです。
- 最期をどう迎えたいかを話し合っておく
- 家族内での役割や希望を明確にしておく
- 専門家に早めに相談しておく
これは誰にでも訪れる“その日”を、後悔の少ないものにするための備えです。
「まだ元気だからこそ、できることがある」――
そう気づいたときが、準備を始める最適なタイミングなのかもしれません。